
「HSPで仕事がつらい。。。」
「仕事がつらい時の乗り越え方を知りたい。。。」
この記事ではこちらの内容をまとめてます。
・HSPの人が仕事をつらく感じる理由
・仕事がつらい時の対処法
・HSPに向いている仕事の環境
本記事の著者


「仕事がつらい…。」そう感じることは誰にでもありますが、HSPの方にとっては、特にその負担が大きいかもしれません。
職場の人間関係に気を遣いすぎたり、環境の変化に敏感すぎたり、些細なことでも深く考え込んでしまう——
そんなHSPの特性が、仕事のストレスをより強くしていることもあります。
私自身もHSPで、さまざまな苦労を経験してきました。



上司や同僚の機嫌を気にしすぎたり、大人数の会議で圧倒されてしまったり…。
しかし、試行錯誤を重ねるうちに、「HSPの自分でも無理なく働ける方法」があることに気づきました。
今では、無理なく毎日楽しく働けています。
本記事では、HSPが仕事でつらいと感じる具体的な理由と、その対処法を紹介します。
自分らしく働くヒントを見つけるきっかけになれば幸いです。
はじめに:HSPとは?


仕事がつらいと感じることは誰にでもありますが、HSPの人にとっては、そのストレスがより強く感じられることがあります。
まずは、「HSPとは何か?」という基本的な部分から理解を深めていきましょう。
HSPの定義と特徴
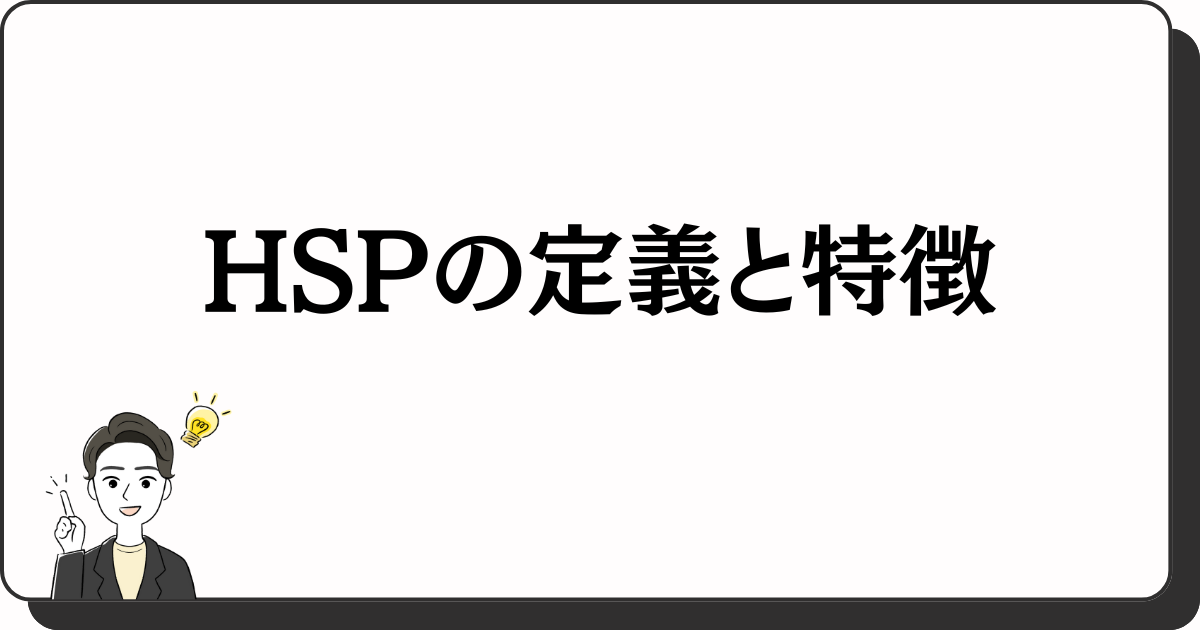
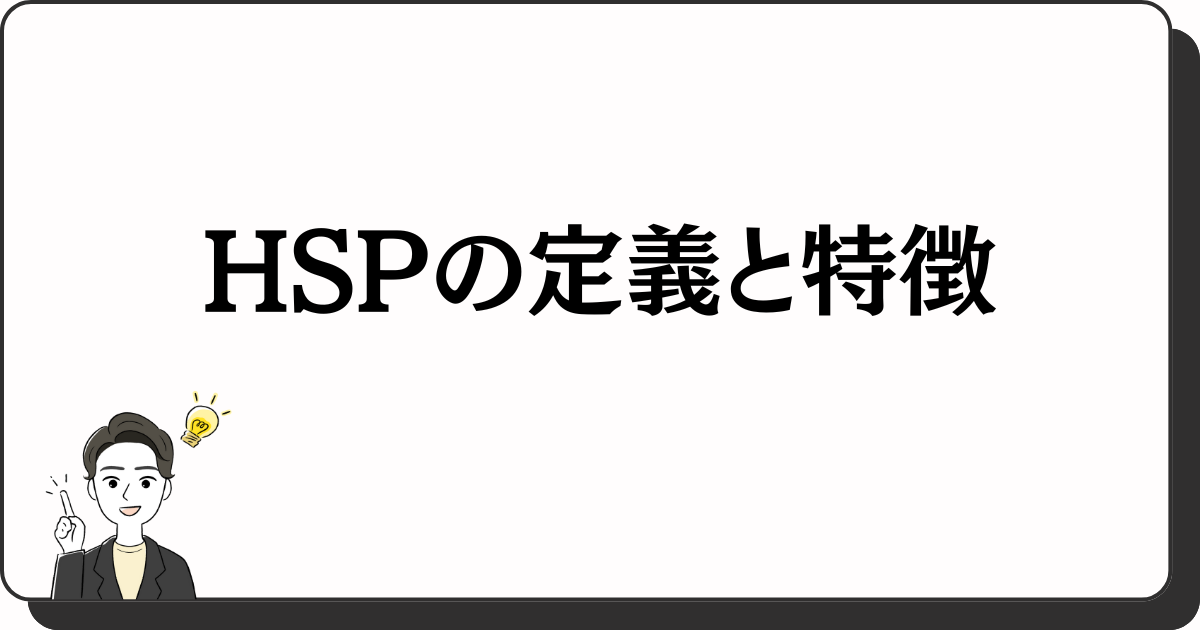
HSPとは?
HSP(Highly Sensitive Person)は、日本語で「とても敏感な人」と訳される概念です。
1996年にアメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士が提唱しました。
HSPは病気や障害ではなく、「生まれつき神経が繊細で、刺激に敏感な気質」を持つ人のことを指します。
簡単に言うと、「人よりも物事を深く感じ取り、細かい変化に気づきやすい性格」のことです。
HSPの4つの主な特徴(DOESモデル)
アーロン博士は、HSPの人が共通して持つ特徴を4つにまとめ、「DOES(ダズ)」モデルと名付けました。
D(Depth of processing):深く考える
HSPの人は、目の前の出来事をすぐに処理するのではなく、じっくりと深く考えます。
例:会議で誰かが発言した内容について、表面的に理解するのではなく、『この発言の背景にはどんな意図があるのか?』と考え込む。
O(Overstimulation):刺激を受けやすい
大きな音、人混み、強い光などの刺激に敏感で、疲れやすい傾向があります。
例:ショッピングモールや満員電車にいると、人の声や広告の音が一気に耳に入ってきて、頭がパンクしそうになる。
E(Empathy & Emotional responsiveness):共感力が高い
他人の感情に敏感で、相手の気持ちを自分のことのように感じることが多いです。
例:友達が落ち込んでいると、自分も同じように悲しくなり、何かしてあげなきゃと焦ってしまう。
S(Sensitivity to subtleties):細かいことに気づく
周囲のちょっとした変化や、他の人が気づかない微妙な違いに敏感です。
例:上司の声のトーンがいつもと違うことに気づいて、『何かあったのかな?』と気になってしまう。
HSPの割合と社会的認知度
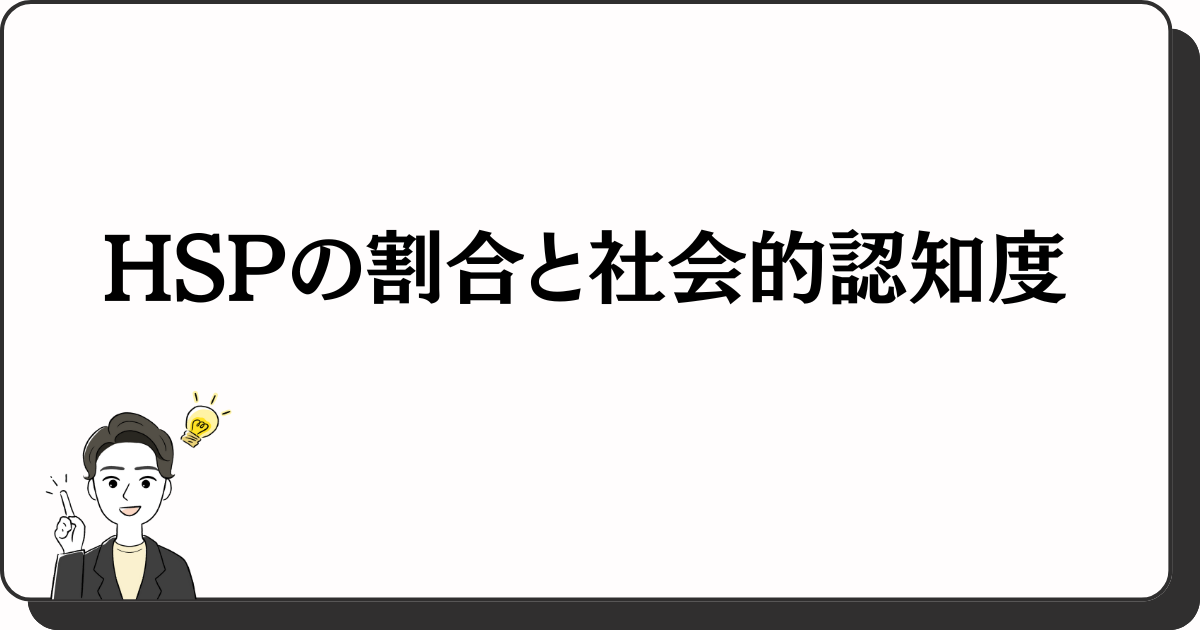
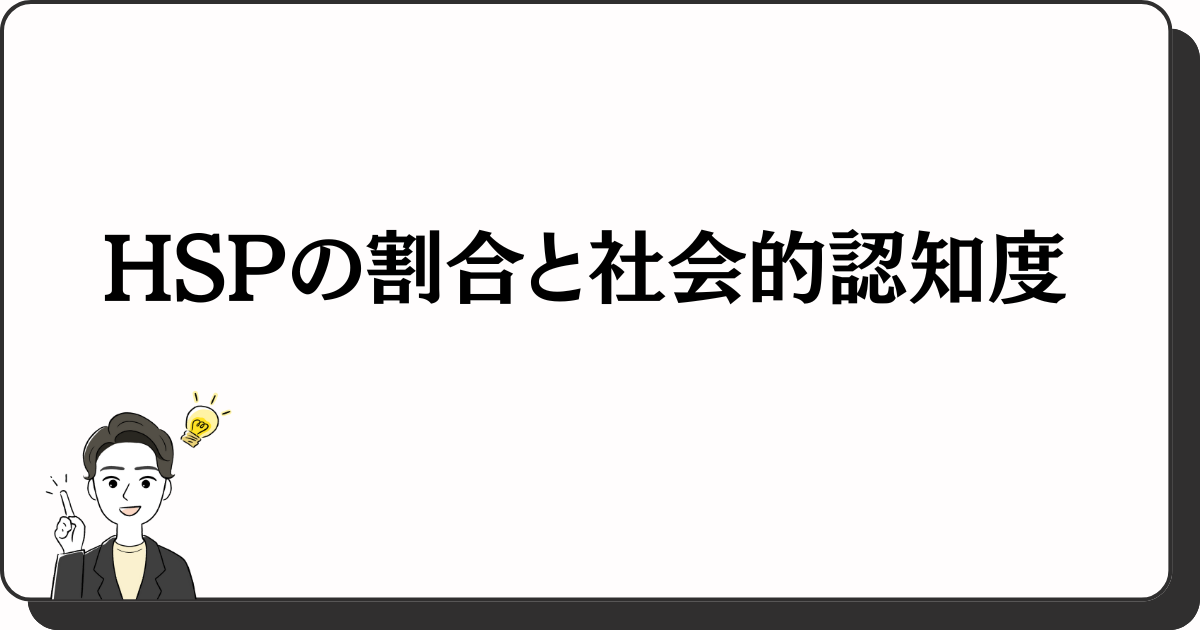
HSPはどのくらいいるのか?
HSPは、全人口の約15〜20%(5人に1人)存在すると言われています。
つまり、クラスや職場に20人いれば、3〜4人はHSPの可能性があるということです。
しかし、HSPの特性は外見ではわからないため、周囲に理解されにくいことが多いのも事実です。
特に日本では、積極的にコミュニケーションをとる「外交的」な人が評価されることが多く、HSPの人が苦しむ原因になっています。
HSPは生まれつきの気質である
HSPは、後天的に身につくものではなく、生まれ持った脳の神経の働き方によるものです。
特に、HSPの人は「扁桃体(へんとうたい)」という脳の部位が活発に働いていることが、科学的な研究でも明らかになっています。
扁桃体は、危険を察知する役割を持つ脳の部分です。
HSPの人は、扁桃体の活動が活発なため、「人よりも早く危険を察知する」という特性を持っています。
そのため、周囲の小さな変化に気づきやすい反面、ストレスを感じやすいというデメリットもあります。
HSPの社会的認知度は上がっている
近年、HSPという概念が広まるにつれ、HSPに対する社会的な理解も進んできました。
「鈍感な世界に生きる 敏感な人たち」などのHSP関連の書籍が世界的にベストセラーになっています。
テレビやYouTubeでもHSPについて取り上げられることが増えています。
また、リモートワークの普及により、HSPが働きやすい環境が整ってきて、「静かな環境で働きたい」「対面の会議が苦手」といったHSPのニーズに合う職場も増加中です。
HSPが仕事でつらいと感じる5つの理由


HSPは、職場で特にストレスを感じやすいと言われています。
ここでは、HSPが仕事でつらいと感じる代表的な5つの理由を詳しく解説します。
職場の人間関係におけるプレッシャー
HSPの人は、職場の人間関係において必要以上にプレッシャーを感じることが多いです。
HSPの人は「共感力が高い」「相手の感情に敏感」「人を傷つけたくない」という特徴を持っているため、人間関係のストレスを通常よりも強く受けやすいのです。
会議で自分の意見を言った後、上司の表情が少し曇ったのを見て、一日中そのことが気になってしまった。
環境の変化や予期せぬ出来事への対応
HSPの人は、急な環境の変化や想定外の出来事に対して強いストレスを感じることが多いです。
HSPの人は「深く考える」という特性を持っているため、事前に準備しないと不安を感じやすいのです。
しかし、職場では急な業務変更や予想外のトラブルがつきもの。
こうした状況に直面すると、HSPの人はパニックになりやすく、通常よりも強いストレスを受けてしまいます。
突然の会議に呼ばれたとき、心の準備ができていなかったため、頭が真っ白になり、うまく発言できなかった。
大人数の会議や社交的な場での疲労感
HSPの人は、大人数が集まる場面で極度の疲れを感じやすいです。
HSPは「音」「光」「人の動き」などの刺激を通常よりも強く感じるため、会議室のざわつきや、複数人の会話が飛び交う環境にいるだけでエネルギーを消耗してしまいます。
さらに、「自分がどう思われているか」を過度に気にしてしまうため、社交的な場がストレスになることもあります。
「話を合わせようと気を遣いすぎて、帰る頃にはぐったりしてしまう」
HSPの人は、大人数の場に長時間いると疲労がたまりやすいです。
ノルマや締め切りによるプレッシャー
HSPの人は、ノルマや締め切りがある環境で強いプレッシャーを感じやすいです。
HSPは「完璧にやり遂げないといけない」という思いが強いため、締め切りが迫ると「もっと丁寧にやりたいのに時間がない」という焦りが生まれ、精神的に追い詰められてしまいます。
「中途半端な資料を作るのが嫌で、あれもこれも考えて時間が足りなくなる」
完璧主義による自己否定感
HSPの人は、完璧主義になりやすく、自分を過小評価する傾向があります。
HSPは「深く考える」「ミスを恐れる」という特性を持っているため、「自分の仕事は本当にこれでいいのか?」と不安になりやすいのです。
また、他人の評価を気にしすぎるあまり、少しでも否定的なフィードバックを受けると「自分はダメだ」と自己否定に陥りがちです。
「上司からのフィードバックを受けたときに、たった1つの指摘に対して、自分のすべてがダメな気がして落ち込んでしまう」
筆者の経験談:HSPとして感じた仕事のつらさ
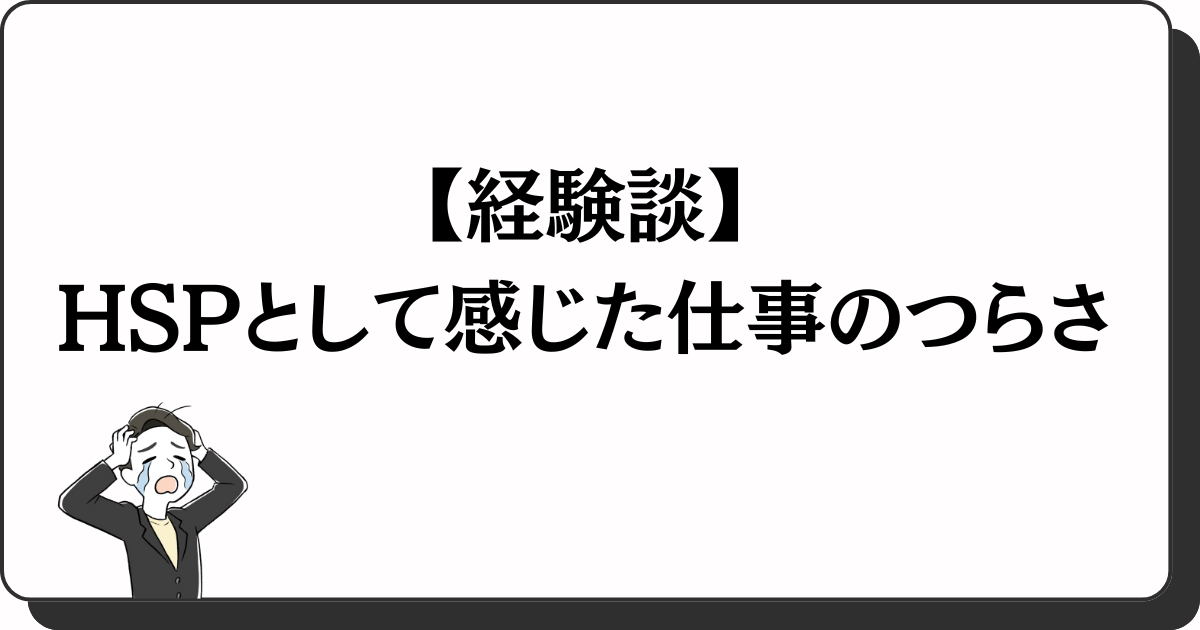
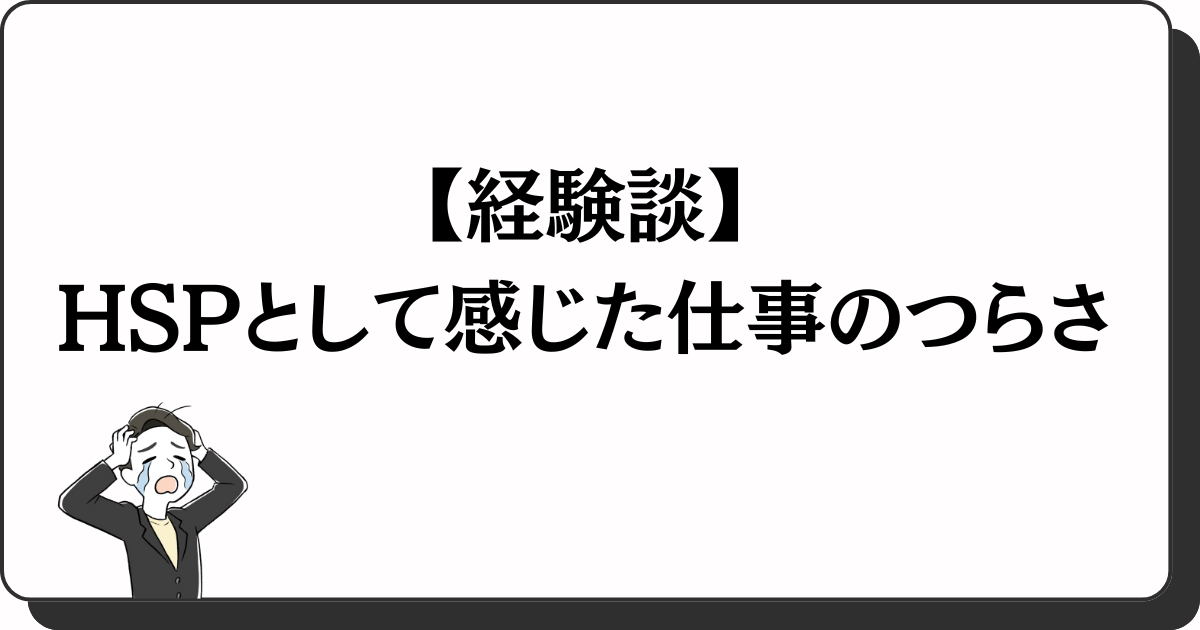
筆者も内向型・HSPで、新卒時代の「営業職」では、仕事がつらくて仕方ありませんでした。
仕事が自分に合わなさすぎて、最終的にはうつ状態と病院で診断され、休職・退職することになりました。
HSPの特性が影響して、仕事のあらゆる場面で精神的な負担を感じていたのです。
ここでは、そんな私が感じた仕事のつらさを紹介していきます。
対人関係
HSPの人にとって、職場の対人関係は特にストレスを感じやすい部分です。
私も例外ではなく、職場の人間関係に過度に気を遣いすぎてしまい、常に神経をすり減らしていました。
上司や同僚の機嫌に振り回される
HSPの人は、他人の感情を敏感に察知するという特性を持っています。
私も職場の空気や上司の表情の変化に必要以上に気を取られ、
「今の発言、怒らせてしまったかな?」
「自分の態度が悪かったかもしれない」
と一日中考え続けてしまうことがよくありました。
また私の職場では、上司からパワハラまがいの厳しいフィードバックを受けることが多く、指摘されるたびに「自分はダメな人間なんだ」と自己否定のループに陥ってしまうことが何度もありました。
雑談や飲み会が苦痛
営業職は、社内外の人と話す機会が多く、雑談力やコミュニケーション力が求められます。
しかし、私はHSPかつ内向型なので、雑談がとにかく苦手でした。
・面談の雑談で話題を見つけられず、気まずい沈黙が続く
・飲み会で盛り上がるノリに合わせられず、ひたすら相槌を打つ
・会議で「もっと積極的に話せ」と上司に言われるたびに落ち込む
こうしたことが積み重なり、「営業職は自分に向いていないな」と痛感しました。
プレゼンテーション
HSPの方に多いと思いますが、大人数に対してのプレゼンテーションが苦手でした。
理由は単純で、たくさんの人の視線を感じて、緊張してしまうからです。
「失敗したら迷惑がかかる…」
「途中で話す内容を忘れたら恥ずかしすぎる…」
このようなネガティブな考えが頭をよぎり、ガチガチに緊張してしまいます。
営業職ではプレゼンテーションをする機会が非常に多く、ある日30人ほどの前で発表することになりました。
しかし、緊張のあまり言葉に詰まってしまい、焦って声がうわずり、お客さんから



「君、大丈夫??落ち着いてね(笑)」
と笑われてしまうという経験をしました。
あの瞬間は今でも思い出すだけで冷や汗が出ます。
「プレゼンが苦手なままではダメだ」と思い、以下のような対策を試しました。
・失敗しても問題ないと楽観的に考える
・場数を踏んで慣れる
・事前にたくさん練習する
しかし、3年経っても大幅には改善されず、今でも大人数のプレゼンには苦手意識があります。
電話対応
電話対応も、HSPの私にとっては大きなストレスでした。
苦手な理由としては、
などが挙げられます。
不機嫌な上司から急に電話がかかってきたとき、本当は理解していることなのに頭の中で整理が追いつかず、咄嗟に受け答えができませんでした。
そのことがきっかけで、説教をいただくことになりました。
そんなことが、数えきれないほどありました。
営業職では電話でのやり取りが避けられませんでしたが、少しでもストレスを減らすために以下の工夫をしました。
・要点を簡潔にまとめる練習をする
・できるだけメールやチャットでの対応を増やす
しかし、社内や取引先との関係上「電話でのやり取りが基本」だったため、苦手意識を完全になくすことはできませんでした。
HSPが仕事のつらさを乗り越えるための対処法


HSPの人が仕事でつらさを感じやすいのは、単に「気にしすぎ」だからではありません。
生まれ持った繊細な気質や特性が、職場環境と合わないことが多いためです。
しかし、「HSPだから仕事がつらい」と諦める必要はありません。
自分に合った対処法を取り入れることで、ストレスを減らし、より働きやすい環境を作ることができます。
ここでは、HSPが仕事のつらさを乗り越えるための5つの対処法を詳しく解説します。
自己理解を深める
まず大切なのは、「HSPとしての自分を理解すること」です。
HSPの人は、職場の環境や人間関係の影響を強く受けます。
しかし、自分が何に対してストレスを感じやすいのか、どのような働き方が向いているのかを把握していないと、無意識に自分に合わない環境で頑張り続けてしまうことがあります。



過去の自分も、自分のことを理解しないまま働いていました。
また、HSPの人は「繊細だからダメなんだ」と思いがちですが、実はHSPの特性は
など、強みとして活かせる部分も多いです。
・大人数の会議が苦手 → 一対一の会話が得意だから、カウンセリングの仕事が向いている?
・急な予定変更にストレスを感じる → 自分のペースで1人で働ける仕事が向いている?
まずは自分の特性をしっかり理解し、「何がストレスになりやすいのか」「どんな働き方が向いているのか」を整理することが重要です。
働き方を工夫する
自分に合った働き方を選ぶことでストレスを大幅に減らすことができます。
HSPの人は、外部の刺激に敏感であり、また急な変化に弱いため、無理にストレスの多い環境で働き続けると心身が疲弊してしまいます。
そのため、できるだけ自分に合った職場環境や働き方を選ぶことが重要です。
- 在宅勤務やリモートワークを活用 → 静かな環境で仕事ができるため、集中しやすくなる。
- フレックスタイム制度を活用 → 自分のペースで働けることで、ストレスを軽減できる。
- 自分のスペースを確保→ できるだけ人と距離を取れる席を選ぶ、イヤホンを活用して雑音を遮る。
HSPの人は、無理に合わない環境に適応しようとするのではなく、自分が快適に働ける環境を作る工夫をすることが大切です。
ストレス管理
HSPの人はストレスを溜め込みやすいため、意識的にリラックスする時間を作ることが重要です。
HSPの人は、職場での小さな出来事や周囲の感情の変化を敏感に察知してしまい、それを無意識のうちに抱え込むことがあります。
そのため、日々のストレスをこまめにリセットしないと、心身の疲労が蓄積してしまいます。
- 深呼吸や瞑想を取り入れる → 心を落ち着ける時間を作ることで、余計なストレスをリセットできる。
- 好きな音楽を聴く・自然の中で過ごす → 五感を癒やすことで、気持ちが安定しやすくなる。
- 適度な運動をする → 軽い運動を習慣にすることで、ストレス耐性が向上する。
HSPの人は、日々のストレスを意識的に解消する習慣を身につけることが大切です。
信頼できる人への相談
悩みを一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが大切です。
HSPの人は「人に迷惑をかけたくない」と思いがちで、悩みを自分の中に溜め込んでしまう傾向があります。
しかし、適切なサポートを受けることで、ストレスが軽減され、解決策が見つかりやすくなります。
- 上司や同僚に「こういう環境だと働きやすい」と伝える → 無理なく働くための配慮をお願いする。
- カウンセリングやHSP向けのコミュニティを利用する → 同じ悩みを持つ人と情報を共有することで、気持ちが楽になる。
つらい気持ちや悩みを、一人で抱え込まないことが重要です。
キャリアの見直しと転職
自分の特性に合った仕事を選ぶことで、ストレスを減らすことができます。
HSPの人は、「自分に合わない仕事」で無理に頑張ると、ストレスを溜め込み、体調を崩したり、仕事への意欲を失ったりするケースも少なくありません。
一方で、HSPの特性を活かせる仕事を選ぶことで、無理なく働ける環境を作ることができます。
私も、新卒で営業職に就いたときは、毎日のストレスが大きく、最終的に精神的に追い詰められてしまいました。
しかし、HSPの特性を考慮して「Webマーケター」に転職したことで、仕事のストレスが大幅に減りました。
自分のペースで作業できる環境が整っていたため、無理なく働けるようになったのです。
適職を見極めるためには、これまでの経験を振り返り、
「どのような場面でストレスを感じやすかったか」「どんな仕事なら無理なく続けられるか」
を整理することが重要です。
HSPが働きやすい職場環境とは


HSPは繊細な性格のため、一般的な職場環境では疲弊してしまい、本来の力を出せない可能性があります。
そのためHSPにとって、働きやすい環境に身を置くことが、仕事をする上で大切になります。
ここでは、HSPが働きやすい職場環境について紹介していきます。
静かで落ち着いた環境
静かで落ち着いた環境は、内向型・HSPの人にとって働きやすい職場環境です。
内向型の人は、外部の刺激が少ない環境で集中力が高まり、深く考えることができます。
また、HSPの人は周囲の刺激に敏感であるため、賑やかなオフィスや雑音の多い環境では疲労感が増してしまいます。
HSPの人がストレスを感じずにパフォーマンスを発揮するためには、静かで落ち着いた作業環境が重要です。
一人で集中できる業務内容
一人で集中して取り組める業務内容は、内向型・HSPの人が最も力を発揮できる働き方です。
HSPの人は他人の感情や言葉に敏感に反応するため、会話や交渉が多い業務では疲れやすくなります。
なので、一人で集中して作業できる仕事であれば、他人の影響を受けにくく、自分のペースで作業に没頭できます。
・一人で作業できる(例:執筆、データ分析、プログラミング)
・デスクワーク(例:リサーチ、資料作成)
・コミュニケーションが最低限(例:メールでのやり取りが中心)
HSPの人が無理なく成果を上げるためには、一人で集中できる業務内容を選ぶことが重要です。
在宅勤務が可能
HSPの人は、人の顔色を伺う習性があり、他人のペースに合わせると疲れやすい特徴があります。
そのため、自分のペースで働くことで、ストレスを最小限に抑えられます。
在宅勤務は快適な環境を自由に作れるため、ストレスを軽減できます。
自分に合った環境を作れる(例:無音、リラックスできる音楽)
人間関係のストレスを減らせる(例:雑談や人間関係に気を使わなくて済む)
自分のリズムで休憩を取れる(例:疲れたら休憩し、集中力を維持)
在宅勤務など、自分のペースで作業できる環境を選ぶことで、無理なくパフォーマンスを発揮できます。
【番外編】HSPに向いている具体的な仕事
HSPの働きやすい職場環境の特徴を満たす、「HSPに向いている具体的な仕事10選」を記事でまとめています。


HSPが向いている仕事として、下記の要素が挙げられます。
・一人で集中できる仕事
・人との接触が少ない仕事
・クリエイティブな仕事
HSPは、大人数で物事を進めるよりも、自分のペースで仕事を進めた方がパフォーマンスを発揮することが多いです。
実際私も、これらの特徴を満たしている「Webマーケター」に転職をした結果、今は楽しく生き生きと働けています。
Webマーケターについては、こちらの記事で紹介をしています。





今の仕事が合わない。。。
という場合は、転職をすることで、働きやすい職場環境を手に入れることができるかもしれません。
まとめ:HSPが自分らしく仕事するために
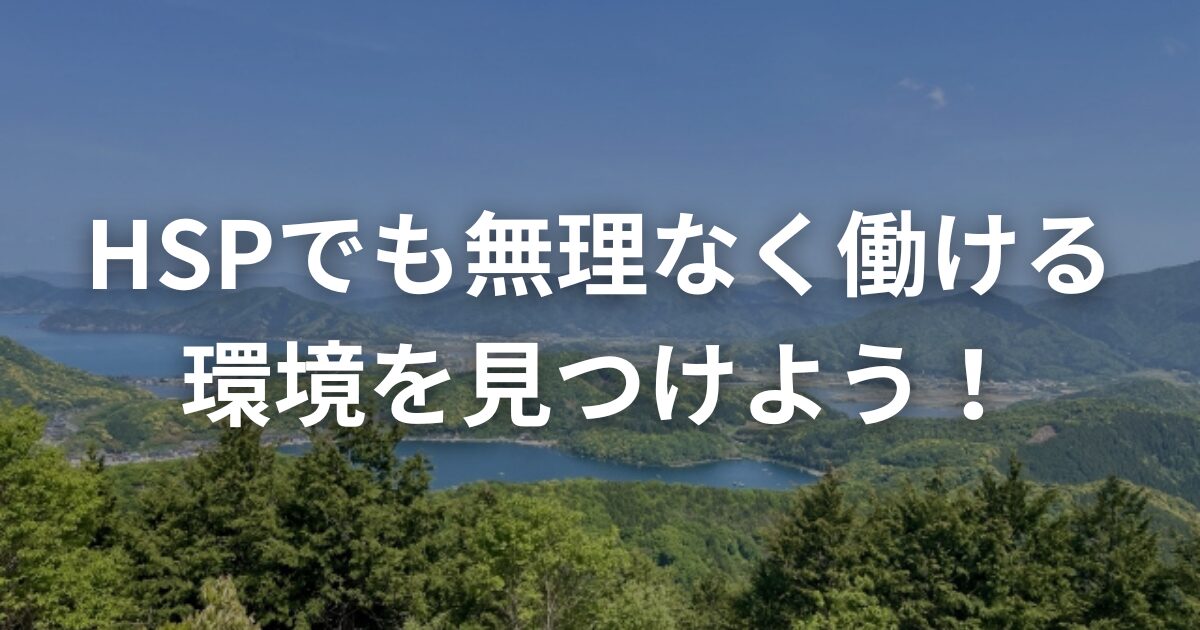
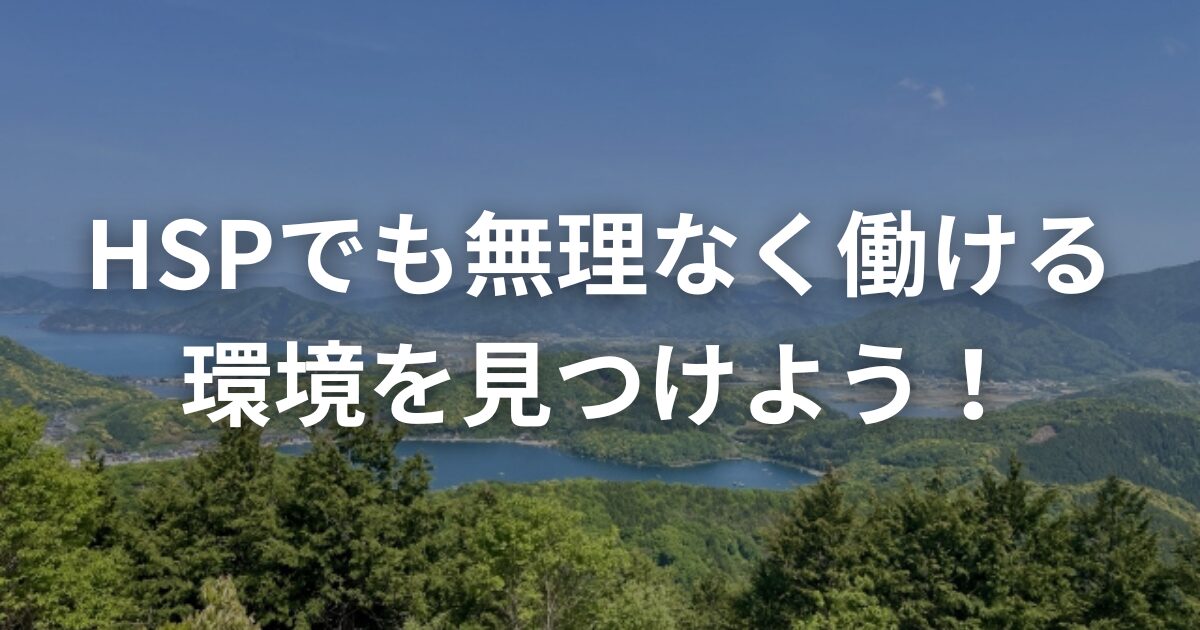
今回は、HSPが仕事をつらいと感じる理由と、その対処法について詳しく紹介しました。
「仕事がつらくて仕方がない…。」
「HSPの自分でも働ける仕事なんてあるのか…。」
このように悩んでいる方も、大丈夫です。
過去の私も同じように苦しみ、



「このままずっとつらい仕事を続けるしかないのか」
と絶望していました。
しかし、自分の特性を理解し、働きやすい環境に身を置くための行動を取ったことで、今では昔とは考えられないほど楽しく働いています。
HSPだからといって、働くことを諦める必要はありません。
大切なのは、「HSPでも無理なく働ける環境を見つけること」です!
そのためには、以下のような対応をすることが重要です。
- 自分がどのような場面でストレスを感じるのかを理解する
- 職場環境や働き方を調整し、少しでもストレスを減らす工夫をする
- 無理に苦手を克服しようとせず、必要なら転職やキャリアの見直しを検討する
今いる環境がすぐに変えられなくても、「できることから少しずつ始める」ことが大切です。
まずは、できることから1つずつ試してみてください!








